【偽・誤情報に触れた人の約半数が「正しい」と認識】
「デマを聞いた2人に1人は、それを正しい情報と信じていた」――。
総務省が発表した、インターネット上の偽・誤情報の拡散に関する全国調査で、こうした実態が明らかになった。委託を除き、同省が全世代を対象にこのような調査を行うのは今回が初めて。
この調査は、2024年3月31日~4月2日にかけて、全国の15歳以上の男女2,820人を対象に実施された。使用されたのは、実際に過去に拡散され、民間のファクトチェック機関「日本ファクトチェックセンター」が偽または誤りと認定した15件の情報。
例えば「WHO事務局長が2024年に『新型コロナに効くワクチンはない』と発言」「イワシやクジラの海岸への大量漂着は地震の前兆や影響」といった内容について、1件以上見聞きしたことがあると答えた人は844人。そのうち、「正しいと思う」「おそらく正しいと思う」と答えた人の割合は、加重平均で47.7%に達した。

【驚き・話題性で拡散される誤情報】
さらに、偽・誤情報に接触した人のうち、25.5%が実際に周囲へ情報を拡散していた。
その理由(複数回答)は「驚きの内容だった」(27.1%)が最も多く、「流行に乗りたかった」(22.7%)、「話の種になる」(21.0%)、「興味深い」(20.9%)といった理由が続いた。
また、「重要と感じた」(20.4%)、「他人に有益と思った」(20.2%)といったように、情報に価値があると信じた上で拡散した人も多く見られた。
専門家の反応は?

この調査結果は、ネット上の「ICTリテラシー向上」を目指す、官民連携の意識啓発プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」の一環で、総務省が公表したものです。
ところが、総務省は調査結果の「概要版」しか公表しておらず、具体的にどのような誤情報を素材に調査したのか、公表していません。この記事に出てくる具体例も、朝日新聞が独自に総務省に取材して確認したとみられますが、そのことも記事には書かれていません。
情報の信憑性を確認する際に最も重要なことは、情報源や根拠資料を確認することです。根拠となる「詳細版」が公表されていない以上(同省の担当課に確認済)、一般市民はこの記事の信憑性も、調査手法等の妥当性も、確認できないことになります。
この記事も、総務省の発表も、「メディア情報リテラシー」の観点からは判断を留保した方がよいということになりそうです。

「火の無いところに煙は立たない」などといまだに言っている人がいます。 インターネットとは、火が無くとも勝手に煙を立たせることができるものだという、リテラシーの無さを露呈する考えです。
子供にスマホを持たせるか問題以上に重要なのがリテラシー教育です。情報の真偽もわからず信じ込んでしまう人間に、インターネットという情報操作に格好の手段が無防備に流通してしまっています。SNSや動画プラットフォーム運営企業が巨額の利益を得る土壌を冷静に見るため、リテラシー教育は欠かせないものとなったと考えます。
大学生に向けて、今できるリテラシー教育を展開していますが、本当はスマホに触りだす前に行うべきだと感じています。
ネットの反応は?

半年前に母がインスタ始めたんだけど、地震予知とかプラスチック米とかこのフライパンは体に悪いとか嘘か実かわからない情報を教えてくるようになってストレスしかない。
こうなんだよ?って言っても聞く耳持たず、占い師とかに洗脳されるとか聞くけど、それがそういうことかと実感してる。
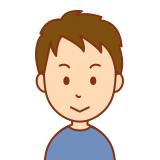
TVも作成側の思い込みを補完するために同じ主張をする自称専門家を探してきて発言させるとか、やってることはただデマを流すよりも悪質って話があるけど。さんまのホンマでっか!?みたいに、ニュースを解説する番組には全部「この番組に登場する情報・見解はあくまでも一説であり、その真偽を確定するものではありません。『ホンマでっか!?』という姿勢でお楽しみ頂けると幸いです。」って注釈を付けるべき。
編集後記

ネットのリテラシー教育に関しては本当真剣に考えた方が良い。国レベルで行わないといけないことと思う。



コメント