黒字でも人員削減 令和の新常識とは
元保険会社勤務・60代男性
「リストラはある程度しないと、将来的に企業の業績に響いてくる」
昭和・平成時代には、赤字に陥った企業による大規模リストラが繰り返されてきました。
しかし令和の現在、黒字を維持している大企業での人員削減が相次いでいます。
パナソニックグループは、今年度中に全従業員の約5%、1万人規模の削減を発表。
国内外でそれぞれ5000人ずつを対象とし、早期退職の募集も行います。
パナソニックHD 楠見雄規社長
「私は雇用に手を付けることは本当にじくじたる思い」
黒字経営の中で、なぜ大幅なリストラに踏み切るのでしょうか。
楠見社長
「このタイミングで経営基盤を変えなければ、10年後・20年後にわたって持続的な成長は見込めない」
また、ロイター通信によれば、アメリカのマイクロソフトもAI事業拡大への備えとして、全世界で約6000人、従業員の約3%を対象にリストラを実施すると報じられました。
街の声を聞くと——
鉄道業界・40代男性
「黒字なら人員削減の必要はないのでは」
「リストラというと、やっぱり暗いイメージがある」
飲食業界・40代女性
「経験や知識が豊富な人材を手放すことになるのではと不安になる」

マイクロソフトが約6000人を削減 全社的な組織再編を実施
米マイクロソフトは、全世界で約6000人の従業員を削減する方針を明らかにした。「管理職の階層を減らすことに重点を置く」としており、組織のスリム化を図る構えだ。
広報担当者によれば、今回の削減人数は同社の総従業員数の約3%にあたる規模で、地域や職位を問わず実施される予定だ。「リンクトイン」を含む傘下の各部門も対象になるという。
同担当者は、「変化の激しい市場で成功を収めるため最善の体制を取れるよう、必要な組織改編を引き続き実施していく」と説明している。
マイクロソフトの従業員数は、2024年6月時点で22万8000人に達していた。同社ではこれまでも優先分野への人材再配置を目的としたリストラを定期的に行ってきた。たとえば、2023年1月には、複合現実(MR)端末「ホロレンズ」やハードウェア部門を含めて1万人規模の削減を実施している。
近年では、人工知能(AI)やクラウドサービス「Azure(アジュール)」の拡大に伴い、データセンターへの大規模な投資が続いている。コスト抑制の必要性もあり、今回の人員削減はその一環とみられる。なお、同社は本会計年度中に約800億ドル(約11兆8200億円)をサーバーファームに投資する計画を進めており、これについては「順調」としている。
今回の人員削減については、米CNBCが先行して報じていた。

黒字企業が6割 広がる希望退職
東京商工リサーチの調査では、2024年に早期・希望退職の募集を公表した上場企業は57社で、前年から約4割増加。そのうちの約6割が黒字企業です。
東京商工リサーチ 情報部 本間浩介氏
「これまでの日本企業では、業績悪化に伴うリストラが一般的でしたが、2024年以降は、黒字経営下でも構造改革に踏み切る企業が増えています」
過去には、2009年のリーマンショック後に2万人超の早期退職が実施され、過去最多を記録。2024年も1万人を超える見込みです。
また、近年ではリストラの対象が30代や勤続年数の短い若手にまで広がっています。
本間氏
「人手不足が叫ばれる一方で、企業は人件費の抑制に強い意識を持っています」
リストラのとらえ方も変化
飲食業界・40代女性
「昔は転職に対してネガティブな印象が強かったけど、今は選択肢が広がっている。その分、自己判断の責任も大きくなっている」
元保険会社勤務・医療業界勤務 60代男性
「“リストラ”の意味も変わりつつある。再就職の機会と前向きに捉える風潮が広まれば、悪い印象ばかりではなくなるかもしれない」
石油会社元役員・80代男性
「バブル崩壊の頃に会社を整理して退職した。従業員300人ほどの会社で、退職金の確保に苦労したのを覚えている」
リストラで創業 老舗そば店にも人手不足の波
一方、リストラが続く中でも、飲食業界では人手不足が深刻です。
「そば処 丸花」の5代目店主・茨和宏さんは、物価高騰に加え人材確保の難しさから、創業以来の危機を迎えています。
茨さん
「そば屋はどうしても人の手がかかる仕事。でも人件費の高騰で簡単には雇えない」
この店のルーツは明治時代初期。川越武士だった先祖が、明治維新で武士の職を失い、知人を頼ってそば屋に転身したという“リストラ創業”の歴史があるそうです。
現在、正社員は1名。厨房担当の65歳の男性が40年近く支え続け、接客は5名ほどのパートが交代で担当しています。
時には常連客が手伝うこともあるといいます。
「リストラゼロ」企業 安定雇用が生む好循環
そんな中、“リストラをしない”方針で雇用と企業の成長を両立している企業もあります。
大阪市の町工場「枚岡合金工具」では、25年前に「リストラゼロ」を宣言。以来、どんな不況でも雇用を守り抜いています。
古芝保治 会長
「どんな状況でも全従業員の雇用を守ると宣言しました」
同社に2年前に中途入社した渡辺諒さん(33)は、長期的なビジョンを描けることにやりがいを感じています。
渡辺さん
「いつ解雇されるか不安な状態では前向きな取り組みは難しい。長期的な視野を持って働けるのは、雇用が守られているからこそ」
古芝会長
「社員の離職が減り、成長意欲も高まる。人間力や生産性が向上し、企業全体のチーム力も強くなっていく」
ネットの反応は?
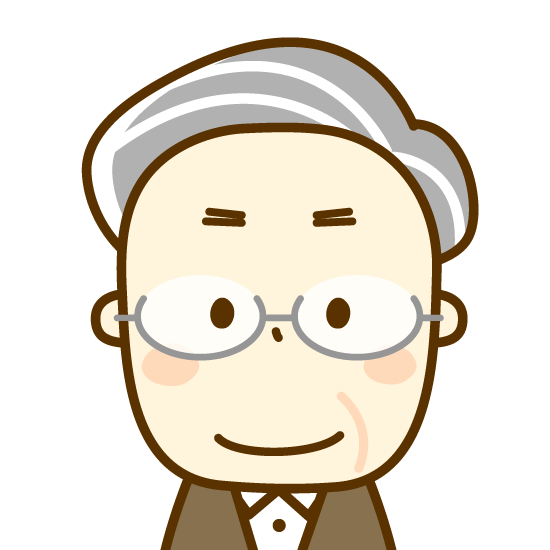
若手ならばそれもいいでしょう。だが、日本の製造業が発展したのは終身雇用の制度の役割が大きかったと自分は思う。雇用が安定しており、時間をかけて技術を学び生かす事ができ良い品質のものを送り出すことができた。流動性が高くなるのは悪い事ではないが、都合良く非正規を増やし使い捨てにしている今の企業のやり方は、日本のものづくり、製造業のを衰退させる一因になっているのでは?メイドインジャパンを誇るのであれば、技術の高さ、信頼で勝負しなければいけないはずだが今は誇れるレベルとは言えない。経営の失敗を社員に押し付け責任を取らない経営陣が多すぎるように思いますね。
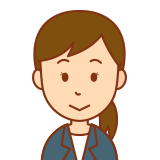
組織を更に良くする為に行うのが本来のリストラ(再構築)であって、業績が悪い会社が行う大量解雇と言うイメージは間違った認識と言っても良いと思います。 特にアメリカの場合は業績好調な企業のリストラが当たり前。その分再就職もしやすく、解雇された人は更に良い条件の企業を目指す事もできるのでウィンウィンの関係になるんですよね。
日本経済を立て直す為にも、業績が良い企業のリストラが当たり前になり、再就職しやすい風土が出来上がって欲しいと思います。

経営者です。と言っても、私以外社員2名とパート2名の小さい会社です。 今期黒字ですが、経費削減はできるか限り頑張ります。ホントはパート1名は…いらないかな。
もう1人は社員にするか悩ましい所。
社会保険料が高すぎて。本人負担分と会社負担分合わせて徴収されますが、えげつない金額。そもそもこれだけ搾取しておいて何に使われてるのか一円単位で出してほしいもんだと思います。 これが大企業だったら、相当な黒字続きの経営でないとキツイだろうなぁ。
政治もガタガタだし、経済だって暗い方向だし、少子化は止まらないし。なんせ未来が暗い。
政治が悪いと悪循環の結果、リストラもやむ得ないのではないかと。
会社が潰れてしまったら元もこうもないですからね。
編集後記

リストラ=マイナスなイメージという風潮がなくなり新たなステップアップのためと捉えられれば労働者として怖いものではなくなりますね。今のような売り手市場の時にそういったイメージ作りが出来ると良いですね。



コメント