シニア世代の間で、「固定電話じまい」の動きが広がっている。スマートフォンの普及により固定電話の役割が薄れつつあるうえ、親族を名乗る詐欺電話など、特殊詐欺への懸念も背景にある。ただ、長年使い続けてきた通信手段だけに、簡単に手放せない気持ちもにじむ。

セールス電話ばかり
茨城県境町に暮らす歯科衛生士の女性(59)は、自宅の固定電話について「万が一、何かトラブルが起きたとき、連絡がくるくらい。以前は命綱のように感じていたのに…」と話す。
10年ほど前に中高生だった2人の娘がスマートフォンを持ち始めてから、家族内の連絡はSNSが主流となった。固定電話の出番はほとんどなくなり、今では歯科医の夫(61)がたまに仕事で使う程度だ。
「友人とのやり取りもスマホが基本。たまに固定電話が鳴ると、『深刻な話かも』と構えてしまう」と女性は明かす。
現在、固定電話にかかってくるのは「テレホンカード余ってませんか」「壊れたバッグ買い取ります」といったセールスがほとんど。不審な電話も増え、女性は不安を感じているという。
夫の退職のタイミングで解約も検討しているが、「災害時などの通信手段を失うことや、解約後に便利さを再認識するのでは」と、ためらいもあるようだ。
「面倒」解約後回し
東京都世田谷区に住む村関不三夫さん(69)も、固定電話にかかってくるセールスに悩まされている。「電話には出ず、着信履歴だけを見て削除している」と話す。
村関さんは、高齢者向けの人材派遣会社「高齢社」を運営している。今年4月に派遣登録者811人を対象に行った調査では、全体の約17%にあたる134人がすでに固定電話を解約していた。「固定電話は役目を終えつつあるのかもしれない」と語る。
自身も解約を検討しているが、手続きの煩雑さから行動に移せていない。村関さんの家にあるのはインターネットを利用する「IP電話」。契約上、電話回線を解約するとネット回線の工事も必要になるため、「不安や面倒さを感じて」躊躇しているという。
中央大学総合政策学部の実積寿也教授は「スマホの普及により、音声通話ではなくメッセージでのやり取りがシニアにも浸透してきたことが影響している。今後も固定電話の利用率は下がっていくだろう」と指摘する。
解約には注意点もある。親しい人に知らせずに突然連絡が取れなくなると、不安を与えたり、関係性に悪影響を及ぼしたりする可能性がある。また、FAXは固定電話回線がないと使用できない。完全にスマホへ移行した場合、通話料が高くなるケースもある。
実積教授は「通信各社には、シニア層に向けた分かりやすい情報提供を進めてほしい」と話している。
20、30代世帯は1割未満
総務省の通信利用動向調査によると、65歳以上が世帯主のシニア世帯における固定電話の利用率は、令和5年時点で82%。依然として高いが、平成21年には99.2%だったことを考えると、15年で大きく減少している。
一方、30代世帯では9.1%、20代ではわずか5.4%にとどまる。スマートフォンやタブレットが当たり前の環境で育った「デジタルネーティブ」世代にとって、固定電話の必要性はさらに低くなっているとみられる。
全国の固定電話契約数も減少傾向にある。NTT東日本によると、契約件数はピークの平成9年11月には約6322万件だったが、令和6年3月時点では(IP電話を含めても)約4963万件まで落ち込んでいる。
ネットの反応は?

60代、固定電話ありますが、常に留守電状態です。家にいても出ません。 大抵は無言で切る、たまに留守電に入っているのはお墓の案内とか家の外装や修理の案内など。
使わなくても基本使用料はかかるので、解約しようとも思うのですが、東日本大震災の時に携帯は使えなくても家電は使えたので連絡手段としてとても助かりました。 また万が一スマホが使えなくなった時の不安からそのままにしており、基本使用料は保険料と捉えて来ましたが、震災からもう14年、色々改善されてあの時のような事はないんですかね。
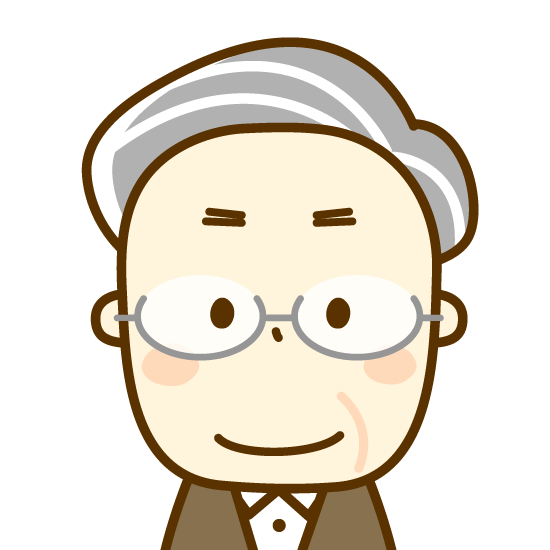
固定電話は留守番設定にしてあります。大抵の営業電話は録音が始まる前に切れるから出る必要が無くて便利。本当に必要な人からの電話は録音が始まってから出ればOK。不要な電話は録音になっても放置、後で消去する。それから、普段氏名や電話番号を書かなければならない時には固定電話の番号を記入。スマホの番号をやたらに書かなくて済むのでスマホの電話はほぼ必要な人からの電話だけになる。固定電話はしばらく手放すつもりはありません。
編集後記

固定電話はずっと留守電で出ないなぁ。本当に伝えたい事あったら留守電にメッセージいれますからね。



コメント