スマホの「ストレージ容量」、PCの「メモリ」「ハードディスク」…
これらはすべて“記憶装置”の仲間です。
でも「RAMとROMの違いは?」「HDDとSSDって何が違うの?」と聞かれると、意外とモヤモヤしませんか?
今回は、記憶装置の分類や特徴、代表的な種類を、イラストとともにわかりやすく解説します!
半導体メモリ(ICメモリ)
半導体チップでできた記憶装置。主にRAMとROMに分かれる。
▶ RAM(Random Access Memory)
- 揮発性メモリ(電源を切るとデータが消える)
- パソコンのメインメモリとして使われる
- データを一時的に保存して高速処理を実現!
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| DRAM(Dynamic RAM) | よく使われる。構造が簡単で容量が多いが、定期的にリフレッシュが必要 |
| SRAM(Static RAM) | 高速・高価。キャッシュメモリなどに使われる |
▶ ROM(Read Only Memory)
- 不揮発性メモリ(電源を切ってもデータが残る)
- 起動時のプログラム(BIOSなど)を保存
- 最近はフラッシュメモリとして再書き込み可能なROMが主流に
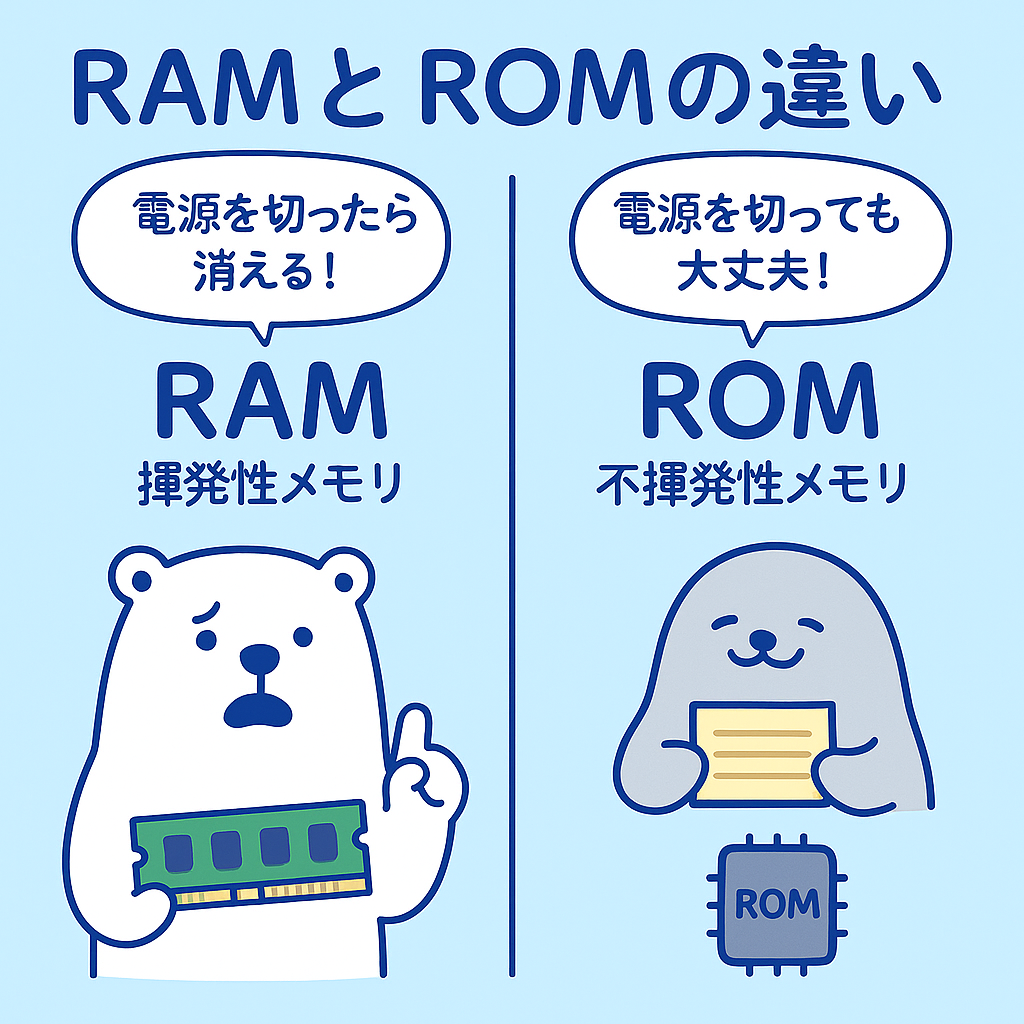
記憶装置のいろいろな種類
| 種類 | 媒体 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| メインメモリ(DRAM) | 半導体 | 処理中の一時記憶。電源を切ると消える |
| キャッシュメモリ(SRAM) | 半導体 | CPUに近くて超高速。一次・二次に分かれる |
| HDD(ハードディスク) | 磁気 | 安価・大容量。回転部ありでやや遅い |
| SSD | フラッシュメモリ | 高速・静音・耐衝撃。価格は高め |
| CD/DVD/Blu-ray | 光ディスク | 主に音楽・映像・データ保存に使用。読み取りは光 |
| USBメモリ・SDカード | フラッシュメモリ | 小型・持ち運び便利。PC・カメラなどで利用可 |
よくある質問(FAQ)
- Qメモリ(RAM)とストレージ(HDD・SSD)は何が違うの?
- A
RAMは一時的な記憶場所で処理中のデータを保存、
HDDやSSDは長期間のデータ保存場所です。
- QROMなのに“フラッシュメモリ”は書き換えられるって矛盾してない?
- A
本来のROMは“読み取り専用”でしたが、フラッシュメモリは書き換え可能なROMとして進化しました。
- Qキャッシュメモリってなくてもいいの?
- A
なくても動きますが、あった方が高速に処理できるので、CPUの性能を引き出すために重要です。
練習問題
Q1. DRAMの特徴として正しいものはどれ?
A. データが消えない不揮発性メモリ
B. キャッシュメモリで使用される
C. 一般的なメインメモリで使われ、定期的なリフレッシュが必要
D. 書き換え不可能な記憶装置
正解:
C
→ DRAMはメインメモリで広く使用され、定期的にリフレッシュが必要です。
Q2. SSDの特徴として誤っているものはどれ?
A. フラッシュメモリを使用している
B. 磁気ディスクを回転させて記録する
C. 衝撃に強く動作音が小さい
D. 読み書きが高速
正解:
B
→ BはHDDの特徴であり、SSDは回転部がない半導体メモリです。
Q3. キャッシュメモリについて正しい説明はどれ?
A. DVDと同じ光ディスクメディア
B. 処理速度は遅いが大容量
C. CPUの近くにある高速メモリで、一次・二次がある
D. USBメモリの一種である
正解:
C
→ キャッシュメモリはCPUの処理を助けるために使われる超高速なメモリです。
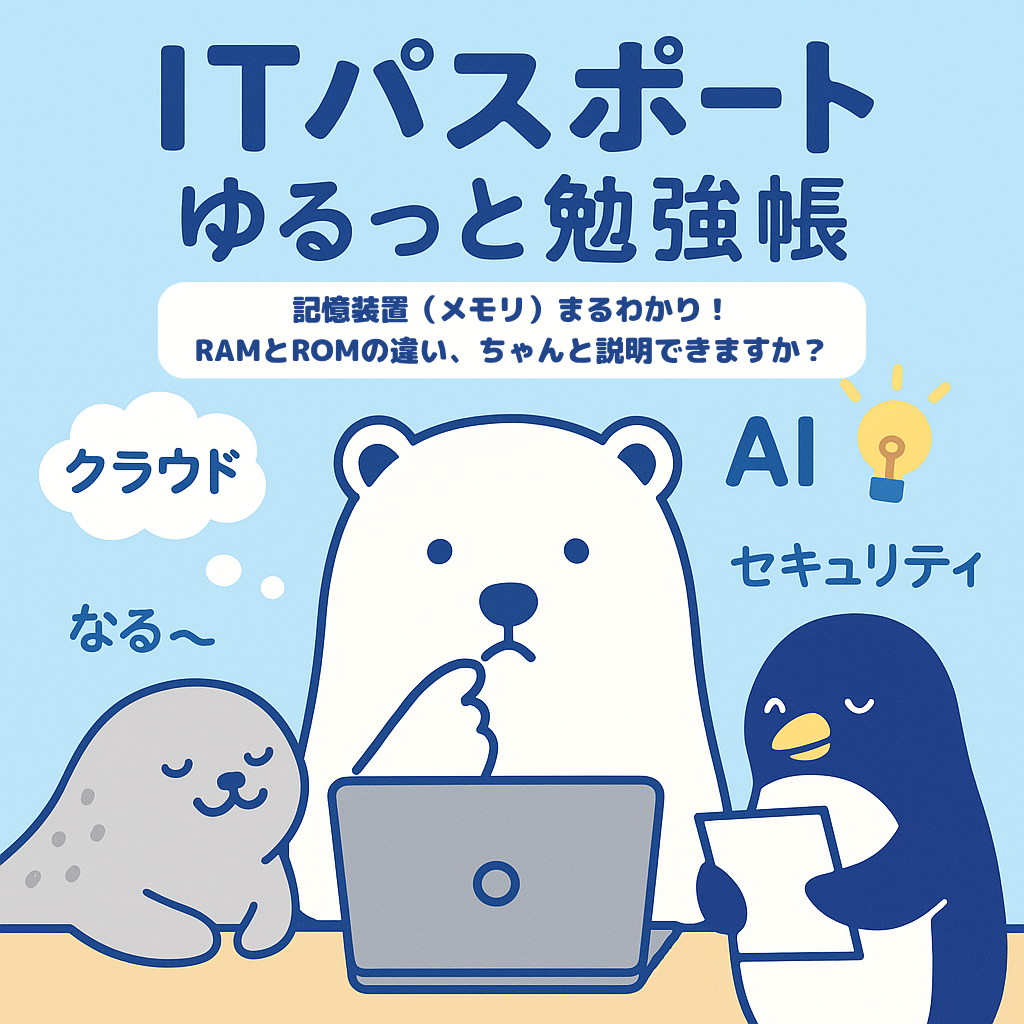


コメント