かつて、クレジットカードで支払いをする際によく耳にした「サインでお願いします」というフレーズ。この“サイン決済”と呼ばれる支払い方法が、2025年3月末をもって廃止されることが決定した。
サイン決済とは、カード所有者が自筆のサインを行うことで、カード会社が取引を承認する仕組みだ。レストランなどでは、自席で伝票にサインして会計を済ませた経験のある人も多いだろう。サインをするだけで決済が完了するため、暗証番号の入力は求められない。
とはいえ、現在のクレジットカード決済では原則として暗証番号の入力が求められる。そのため、万一暗証番号を忘れてしまった場合の代替手段として、「暗証番号スキップ(PINバイパス)」という機能が用意されていた。この機能がまさに“サイン決済”なのである。

サイン決済の利点は何だったのか、暗証番号入力はなぜ定着したのか
「サイン決済」は、利用者が席を立って暗証番号を入力する手間を省ける、便利な決済方法として利用されていた。わざわざカードリーダーのある場所まで移動する必要がないため、特に飲食店などでは重宝されていた。
この方式には他にも利点があり、不正利用が発生した際には、カード裏面の署名とレシートに記されたサインを照合することで、本人による利用かどうかを確認できる。また、筆跡が明らかに異なる場合には、店舗やカード会社が不正利用を疑う手がかりとなっていた。
当初はあくまで特例的な対応として導入されたサイン決済だったが、店舗側・利用者側の双方にとって使い勝手が良かったため、フルコースのレストランやホテルのビュッフェといった場面で広く普及していった。特に、レジでの精算が不要な店舗では、サインによる決済が一般的だった。
では、なぜ暗証番号の入力がここまで定着したのだろうか。
日本では、クレジットカードのセキュリティを強化する目的で、ICチップ付きカードへの移行が進められていたが、その動きは欧米に比べて遅れていた。しかし、2020年の東京オリンピックを見据えてICカード対応が急ピッチで進められ、店舗にも対応が義務化された。その過程で決済端末の切り替えが進み、暗証番号入力が一般化していったのである。
テーブル会計のレストランは、モバイル決済端末の導入が有効に
ここでは、店舗側が抱える懸念点についても触れておきたい。サイン決済が2025年4月以降に廃止されることで、「サイン決済」が使えなくなる店舗が増えると見込まれている。これまでテーブル会計を採用していた高級レストランなどでは、代替手段として新たにレジを設置するか、顧客を決済端末の設置場所まで案内する必要が出てくるだろう。
こうした手間や不便を軽減するためには、据え置き型ではなく、持ち運び可能なモバイル型の決済端末を導入することが効果的だ。近年では、クレジットカードだけでなく、コード決済や電子マネーといった多様な支払い手段が普及しており、店舗側はこれら複数の決済方法に対応した「オールインワン型」のモバイル決済端末を選ぶことができる。
たとえば、三井住友カードが提供する決済プラットフォーム「stera」では、オールインワンモバイル決済端末「stera mobile」が展開されている。この端末には5インチのHDカラータッチパネルが搭載されており、クレジットカードのほか、PayPayやSuica、IDといった各種決済サービスにも対応。無線通信(LTE)も利用可能なため、柔軟な運用が可能だ。
なぜ暗証番号スキップ(PINバイパス)が廃止されるのか
では、なぜ「サイン決済」が2025年3月末をもって原則廃止されることになったのか。その背景について、利用者の視点から見ていこう。クレジットカード業界の団体である「日本クレジット協会」は、2025年4月から「暗証番号の入力がないクレジットカードは(原則)利用できなくなる」と案内しており、安全性の観点から次のように説明している。
「お店でのカード不正利用の防止、お店のイメージアップ、カード会員様の安心・安全なクレジットカードライフのためにも、暗証番号入力を推進しましょう」(日本クレジット協会)
また、日本クレジット協会が2022年に実施した消費者意識調査によれば、「サイン決済ができなくなったら困る」と回答した人は約3割で、これは前回の調査とほぼ変わらない結果だった。
さらに調査では、「カード会員の8割超が暗証番号を把握している」ことが明らかになり、暗証番号を忘れる人が少ないことが示された。また、カード会員の約8割が「カードを偽造されにくい」「カードを悪用されにくい」といったセキュリティ上のメリットを評価しており、安全性への意識が高まっていることがうかがえる。
サイン決済は、暗証番号を忘れた際にも利用できる方法として活用されてきたが、不正利用があった場合、筆跡を確認することで本人確認が可能とされていた。しかし、第三者が本人のサインを模倣してしまえば、その確認方法も有効ではなくなる。さらに、本人であってもサインを間違えて訂正したり、上書きしたりした場合には、そのカードが使えなくなるケースもある。
全てのクレジットカードで暗証番号を求められるワケではない
誤解を避けるために補足しておくと、「サイン決済」が原則廃止されたからといって、すべてのクレジットカード決済で暗証番号の入力が必須になるわけではない。現在、海外では主流となり、日本国内でも普及が進んでいる「タッチ決済」では、一定金額以下の支払いであれば、本人認証なしで利用できる仕組みとなっている。
このタッチ決済における利用上限額は、利用する店舗やカードブランドによって異なるが、一般的には1万5000円未満であれば暗証番号を入力せずに決済可能だ。ただし、1万5000円を超える取引では、暗証番号などの本人認証が必須となる。
暗証番号を忘れたらどうすべきか
では、万が一クレジットカードの暗証番号を忘れてしまった場合、決済はできなくなるのだろうか? 前述の通り、例外を除き、暗証番号は基本的に必須となる。そのため、暗証番号が不明なままでは決済できない。また、暗証番号を複数回間違えると、セキュリティ対策としてカードがロックされ、利用できなくなってしまう。暗証番号に不安のある人や思い出せない人は、事前に確認しておくと安心だ。
たとえば楽天カードの場合、「楽天e-NAVI」の「カードの暗証番号の照会」から確認が可能。この際、カード裏面に記載されている3桁(American Expressは4桁)のセキュリティコードが必要となる。
また、自動音声専用ダイヤル(0120-30-6910)からも照会が可能で、「3」の各種照会を選び、「カード番号」と「生年月日」を入力した後、「5」のカード暗証番号の照会を選択することで、確認手続きが進められる。
PayPayカードの場合は、PayPayアプリまたはWebサイトから手続きできる。アプリでは、「暗証番号の確認(郵送)」を選び、登録住所を確認して「郵送を依頼する」をタップ。Webサイトでは、会員メニューの「管理」→「暗証番号の確認(郵送)」へと進む。手続き後、カードの暗証番号が記載されたハガキが1週間ほどで送付される。
クレジットカードの暗証番号、覚えていない人は確認を
このように、「サイン決済」はカード所有者のサインによって決済が承認される方式として長年利用されてきたが、より安全かつ効率的な決済手段の普及により、その役割を終えつつある。暗証番号を覚えていない人は、今のうちに確認しておくことをおすすめしたい。
専門家の反応は?

結局、クレジットカードの読み取り機が小型化・無線化して、客のテーブルまで持ってこられるようになったのが決め手だったのでしょうね。セキュリティとしては真似が容易なサインより暗証番号のほうが良いのは言うまでもありませんが、肝心の番号が容易に推測できるものだと意味が無くなってしまうかもしれません。やや古い調査ですが、2012年の時点では「1234」「1111」「0000」「1212」「7777」あたりが頻出する番号とされていました。最近では登録時にこの手のははねられてしまうような気がしますが、誕生日等も推測可能ですし、いずれにせよ注意が必要でしょう。
ネットの反応は?
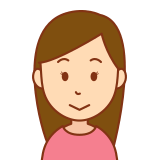
今までも、きちんとしたレストランの場合はテーブル会計であっても、小型の決済端末を担当者がテーブルに持ってきて、その場で端末にクレジットカードを挿入し、客に暗証番号を押してもらっていましたけどね。そういった既に対応済みのレストランも多いと思います。
クレジットカードを預かって、店の裏側に消えていく古くからのやり方だと、不正利用される恐れもあったため、目の前で決済するほうが客にとっても安心だと思います。

暗証番号忘れた本人です。笑)
カードは複数枚持ってますが、いつもサインで済ませてきました。 今、せっせと暗証番号照会の手続き中です。
記事にもありましたが、楽天カードはアプリで調べる事が出来ましたが、それ以外はコールセンターに電話して郵送での回答。携帯からだと0570のナビダイヤルがほとんどで、都度電話料金がかかるのが地味にストレス。キャリアの契約に組み込まれている通話料無料プランにはナビダイヤルは含まれない。
暗証番号を決める時、自身の誕生日や電話番号はダメと言われた場合もあり、家族の誰かの誕生日にしたような~?の曖昧な記憶。
いっその事、全てのカードの暗証番号を娘の誕生日で揃えたいと思い、暗証番号変更しようとしても、カード再発行のため手数料がかかるらしい。
悩ましい…
編集後記

暗証番号忘れてしまったカードはメインのカードでなきゃ面倒で手放したくなっちゃう



コメント