医師の立ち会いのもと、飲酒後の体内にアルコールがどの程度残るのかを検証した。
被験者は500ミリリットルの缶ビール3本を摂取。飲酒後に呼気中のアルコール濃度を測定したところ、1リットルあたり0.3mgを記録。これは酒気帯び運転の基準値の2倍に相当する。
その後6時間が経過。被験者は
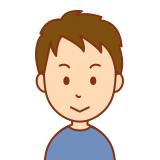
飲んだ直後のふらつきも消え、かなり頭もすっきりしている
と話していたが、実際に測定すると呼気1リットルあたり0.15mgと、依然として基準値を超えていた。
検証に立ち会った「おおひら内科クリニック」の大平俊一郎院長は

大平俊一郎院長
頭がすっきりしていると言っていたが、それが結局酒気帯びの0.15mg/lという呼気濃度。頭がすっきりしてるいからもう大丈夫だと思わないでほしい
と警鐘を鳴らした。
睡眠中はアルコール分解が遅くなる
個人差はあるものの、アルコール20g(ビール500ml、日本酒1合、ウイスキーダブル相当)を摂取すると、体内で分解されるまでに約3時間半かかるとされる。さらに、睡眠中はアルコールの分解が遅くなるため、夜遅くまで飲酒した場合、翌日の運転には注意が必要だ。
おおひら内科クリニックの大平俊一郎院長は

大平俊一郎院長
判断力の低下や注意力の低下、情報処理能力の低下などがある。運転をするならお酒を飲まない。翌朝運転することがあったら飲まないというのが一番いい
と警鐘を鳴らしている。
判断が曖昧な危険運転致死
危険運転致死傷罪が適用されるケースには曖昧な部分が多く、要件の厳しさや裁判所の判断のばらつきが問題視されてきた。
こうした状況を受け、鈴木法務大臣は2025年1月28日、危険運転致死傷罪の適用要件について、速度や体内アルコール濃度などの明確化を進める方針を表明。2025年2月の法制審議会に諮問し、今後の法改正に向けた議論が本格化する見通しだ。
ネットの反応は?
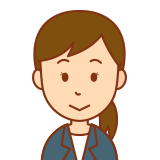
飲酒運転による死亡事故は、単なる過失では済まされないと思います。酒を飲んで車を運転すれば判断力が鈍り、事故の危険性が上がることは周知の事実で、それでも運転した結果、人の命を奪ったのなら、厳しく罰せられるべきです。明らかな殺意がないにしても、人を死なせてしまう可能性を認識した上で行われたなら、責任重大です。 現状の刑罰では、被害者の無念を晴らすにはあまりにも軽すぎます。飲酒運転による死亡事故は、殺人罪と同等レベルの重罪とみなし、厳しい罰則が必要ではないでしょうか。
二度とこのような事故が繰り返されないことを切に願います。

飲酒運転もだけど、はねて逃げて、飲酒を隠すために時間を空けてから名乗り出た場合、またはそう判断される場合は罪を厳しくして欲しい。 飲酒して運転してはねた後にコンビニに寄って、それを隠すために酒買ってその場で飲んだケースもあると読んだことがある。
編集後記

車に呼気チェックの機能つけて検出されたらエンジンかからないようにするくらいした方が良いですね。



コメント