株式や投資信託などによる売却益や配当が非課税となる「少額投資非課税制度(NISA)」を積極的に活用するシニア層が増えています。こうした動きを「シンニーア(シニア+新NISAの造語)」と呼ぶ声もあります。従来のNISAは長期運用が前提とされるイメージから、高齢者にとってはややハードルの高い制度でした。
しかし、令和6年1月からは非課税投資枠の拡充などを含む「新NISA」がスタートし、退職金などのまとまった資金を保有する高齢者層の注目を集めています。老後の資産形成を目的とした投資への関心が高まり、シニアマネーの市場流入が加速しています。

新NISAを活用するシニア層が増加中!
金融庁のデータによると、令和6年9月時点でのNISAを通じた買い付け額は、60代で2兆5520億3682万円、70代では1兆7341億9812万円にのぼりました。これに対し、新NISA開始前の5年間における通年の買い付け額は、60代が9653億9190万円、70代が7393億1805万円であり、わずか1年足らずで両世代ともに2倍以上へと急増しています。
NISAの利用者数も右肩上がりです。令和6年9月時点のNISA口座数は、60代で369万1248件、70代で285万8589件となり、令和5年12月時点と比較すると、それぞれ約50万件、約23万件の増加となりました。こうした背景には、新NISAによる制度の拡充がシニア層の投資意欲を喚起したことがあると考えられます。
NISAは、政府が個人投資家の層を広げ、家計の安定した資産形成を支援することを目的に、平成26年に導入された制度です。令和5年までは「一般NISA」で株式などを、「つみたてNISA」で一定の投資信託を購入でき、それぞれに非課税期間と投資上限が設定されていました。
令和6年から導入された新NISAでは、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」という新しい構成となり、非課税限度額が大幅に引き上げられました。さらに、売却益や配当に対する非課税期間は無期限とされ、両枠の併用も可能となっています。
従来、NISAは「長期・積立・分散」といった投資の基本方針に則った制度であるため、高齢者の中には「今から始めても遅い」として敬遠する傾向も見られました。しかし、人生100年時代を迎え、老後の時間が長くなる中で資産形成の重要性が再認識され、新NISAを機に退職金などを活用して資産運用を始めるシニア層が増えています。
NISA運用のメリット・デメリットは?
例えば、退職金などから600万円を投資に充て、65歳から毎月5万円ずつ10年間積み立てたケースを考えてみましょう。三井住友銀行の「税軽減シミュレーション」によれば、年利3%で運用した場合、得られる運用益は98万9595円に達します。このとき、新NISAの非課税制度を活用することで、課税される場合に比べて約20万1036円多く受け取れる計算になります。
もっとも、高齢期に入ってからの投資に不安を感じる人もおり、運用利回り次第では元本割れのリスクもあります。生活資金まで投資に回すことは避けるべきです。
野村証券の磯崎博志ストラテジストは、米国の代表的な株価指数の過去の動きを基に積立投資の効果を検証。その結果、相場が堅調だった近年では高い効果が見られた一方で、リーマン・ショックのような市場の大幅下落時には元本割れも起きたものの、損失は一定範囲に収まっていました。磯崎氏は「積立投資は、長期的な利益を目指すうえで有効な戦略」と評価しています。
では、シニア層が資産運用を行う場合、どのような投資商品を選べば良いのでしょうか。三菱UFJ信託銀行の勝盛政治氏は、「まずは運用の目的を明確にすることが大切」とアドバイスします。
将来への備えを重視するなら、つみたて投資枠を利用し、株式資産の比率が高く、長期的な資産形成に向いた商品を選ぶのが適しています。一方で、運用の成果を日々の生活に役立てたいという場合には、つみたて投資枠または成長投資枠のどちらでも、価格が比較的安定し、定期的な利息が見込める債券を中心に構成された商品を選ぶのがよいとされています。
また、「投資経験が少なく不安を感じる方には、分散投資が可能なつみたて投資枠の商品が向いています。どの投資枠を利用する場合でも、安定性を重視するなら債券を一定割合含むことがポイントです」と勝盛氏は語ります。
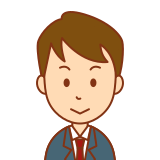
勝盛政治氏
現役世代のようにどんどん増やすことを目指さず、資産を少しでも増やすといった観点で、余裕資金を新NISAで活用するのも選択肢だ
と、勝盛氏はシニア世代の新NISA活用に期待を寄せています。
専門家の反応は?

円安による外貨建て資産と新NISAや株高を背景にした投資信託の増加で、日本の個人が保有する金融資産は2230兆円となり過去最高を更新しました。 2024年は、日経平均が市場最高値を示したこともあり、日本株の利益確定売りが多く見られ売り越しました。しかし、外国株の投資信託が買われ、合わせて10兆円程度の買い越しとなっています。
この買い越しが株高や円安をもたらしている可能性があります。
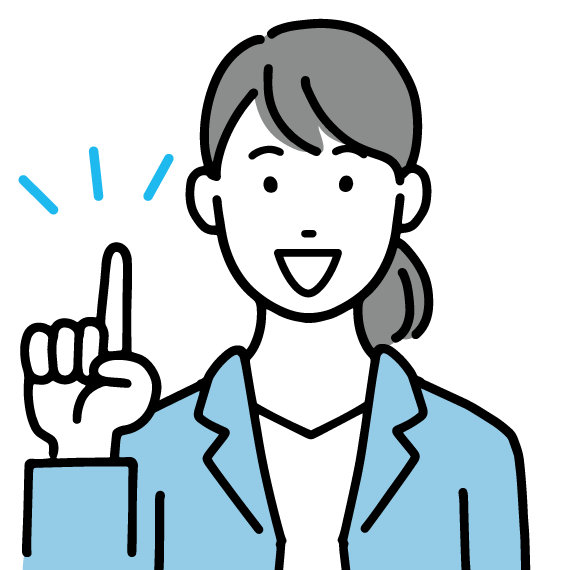
以前、「人生100年時代の老後資金セミナー」に95歳の方が参加されたことがあり驚いたことがあります。「3~5年以内に使用する予定の資金は投資に回さない」という原則に従えば、人生100年時代にインフレリスクに備える意味でも、運用リスクを抑えた長期投資はむしろ必要なものでもあるといえます。シニアのNISA口座数や買い付け額が増加しているのは、納得できる現象だと思います。ただし、リスク軽減効果のあるつみたて投資枠を優先すること、余裕資金で行うこと、の大原則は守って行うべきです。
余談ですが、このネーミングなんとなくしっくりこないのは私だけ?
ネットの反応は?

NISAを積極活用するシニア「シンニーア」が増えて老後の資産形成が加速している。政府、財務省はNISAに課税したり、年金改革で基礎年金の給付水準を底上げするために厚生年金の積立金を使おうとしている。そもそも厚生年金は長年労働者がコツコツと高い保険料を支払ってきて国民年金と差があるのは当然である。国会議員はNISA徴収金や厚生年金の積立金を勝手に使える自分達のお金と勘違いしている。老後の生活費のために長年真面目に働き高い厚生年金保険料を納めてきた労働者が報われる政策を取って欲しい。
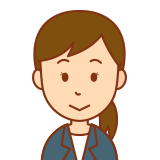
シニア世代が投資をする事自体は問題無いとは思いますが
経験が無いシニア世代がいきなり投資を始める事は、 金額も大きくなるでしょうし、失敗したとして取り戻す時間も少ない為 ご自身の適性等をよく考えられた方が良いと思います。
退職金振込後の銀行からの電話には要注意して頂きたいです。

退職して十四年になり、それなりに株も保有し、幾ばくかの配当収入もあります。しかし、老後の資金を投資に回すのは勧めません。老後は攻めるより守りの方が重要だと思うからです。長い目で見ればリターンは望めますが、短期でリターンを求めるのはリスクが大きい。ローリスク、ローリターンが良いと思います。出費を抑え、心配なら低賃金でも働いた方が精神的に穏やかに過ごせます。
編集後記

現役世代は最悪稼げば取り返せるってなるけど引退した後、いくら余剰資金とはいえ、元本割れとかしたら精神的にまいりそう。。



コメント