2025年は日本の「ライブコマース元年」になるかもしれない
コロナ禍を契機に市場が拡大し続ける中、2025年は日本のライブコマースにとって大きな転機の年となりそうです。特に6月には、TikTokを運営するバイトダンスが「TikTok Shop」を日本で本格展開する予定です。既に月商2億円を超える事業者も登場しており、EC業界に新たな熱気が生まれています。
ライブコマースとは、ライブ配信とオンライン販売を掛け合わせた販売手法で、商品を動画で紹介しながら視聴者とリアルタイムでやり取りし、購買を促すものです。視聴者がその場で質問し、すぐに購入できるという「双方向性」と「即時性」が支持を集めています。
アリババによると、中国のライブコマース市場は2021年時点で約33兆円規模にまで成長。一方日本ではまだ規模は小さいものの、2023年時点で約3000億円弱に達し、年々伸びを見せています。背景には、5Gの普及による高画質視聴の一般化や、SNS文化の定着でネット購入への心理的ハードルが下がったことが挙げられます。

大手企業が続々と参入
日本におけるライブコマースの始まりは2017年頃。メルカリや楽天などが先行してサービスを立ち上げましたが、当時は市場がまだ成熟しておらず、いずれも短期間で終了となりました。
転機は2020年のコロナ禍。外出自粛による新たな販売チャネルとしての需要が高まり、アパレルやコスメ業界を中心に導入が進みました。
その流れを加速させたのが、ユニクロの「UNIQLO LIVE STATION」です。店舗スタッフが着こなし提案などをライブで伝えるこの配信は、2024年には年間視聴者数2500万人を超えました。同期間のEC売上も前年同期比10.9%増の824億円となり、ライブ配信が貢献したと見られています。
ニトリも「ニトリLIVE」でライブ中にクーポン配布やアンケートを行い、録画をECサイトにも活用。視聴者数は642万人に達し、EC売上は前年同期比12.8%増となりました。
ライブ配信を通じてブランドの魅力をダイレクトに伝えられること、また、商品の実演を通じて「試せない不安」を払拭できることが、大手参入の背景にあります。
ECサイトの数倍の購入率を記録
大阪に本社を構えるCellest(セレスト)は、ライブ配信者の育成とマネジメントを行う専業事業者です。2024年4月には売上が2億円を超え、事業が急拡大しています。
専用スタジオの整備や、視聴データの分析を通じて成約率を高めてきた同社では、平均視聴者1万3000人を誇る「ぞうねこちゃんねる」や、大きめサイズのアパレルを扱う「アヒルのライブマーケット」などが人気を集めています。
特筆すべきはコンバージョン率の高さです。これらのチャンネルでは約16%に達しており、一般的なECサイトの1~3%と比較しても驚異的な数値です。Cellestの佐々木社長は「商品への理解と信頼が深まることで購入につながる」と語ります。
実演が可能なコスメやアパレルとの相性は良く、無形商品であっても、例えばあるフィットネス配信では1時間で200人の入会を達成するなど、その影響力は侮れません。
なお、視聴者の多くは35歳以上の女性が中心。SNSよりも信頼性のある説明を重視する層に支持されていることも、成約率の高さを後押ししています。
「楽しさ」と「販売」の絶妙なバランスが鍵
ライブコマースで重要なのは、エンタメ性とセールス要素のバランスです。セールスばかりでは飽きられ、エンタメ寄りすぎると購買につながらないからです。
「ぞうねこちゃんねる」の熊田氏は、視聴者参加型のクイズや掛け合いを交え、「見る楽しさ」と「買いたくなる気持ち」の両立を工夫していると語ります。
また、ライブコマースはアドリブ力も重要です。録画された動画とは違い、リアルタイムで質問やコメントに応じることで信頼関係が生まれます。
朝配信も功を奏しています。「ぞうねこちゃんねる」では朝6時からの配信開始により視聴者数が倍増。アヒルのライブマーケットでは100日連続の朝配信で新規顧客が5.5倍に伸びるなど、時間帯の工夫も成果に直結しています。
一方で課題もあります。配信経験者が少ないこと、SNSプラットフォームの仕様変更への対応など、発展途上ならではの壁も存在します。
専用モール「WABE」でインフラ化を目指す
Cellestは2024年4月、ライブコマース専用アプリ「WABE」をリリースしました。これまでライブ機能を後付けしたECサイトでは、操作の煩雑さがネックとなっていましたが、WABEでは視聴・決済・在庫管理を一体化することで、購入までの導線を大幅に簡略化しています。
「WABE」は、“Watch・Ask・Buy・Enjoy”をコンセプトに、操作性と楽しさを両立。ライブコマースを「インフラ」として定着させることを目標としています。
「ライブコマース元年」は現実となるか
ライブコマースは、商品の魅力をリアルに伝える販売手法として、今後ますます注目を集めそうです。購買力の高い35歳以上の女性層に直接アプローチできるという点でも、事業者にとっては大きなチャンスとなります。
また、地方特産品や説明が必要な商品など、これまでEC化が難しかった商材も、ライブを通じて販路を広げることが可能に。2025年の「TikTok Shop」日本展開をきっかけに、ライブコマース市場の拡大は加速していくでしょう。
この新たな販売チャネルをどう活用するかが、今後の競争力を左右するカギとなるかもしれません。
ネットの反応は?

昔から生放送のテレビショッピングや店頭での実演販売があるので発想自体に何ら目新しさは無いと思います。 それよりも看過できないのはTikTokがショッピングサービスを始めるなど、最近は中国資本のECサイトが勢いを急加速させている事ですね。 気が付けば色んな所に中国のネットサービスが入り込んでいるので、不安を感じている人も多いと思う。
個人情報が適切に取り扱われるかなど、懸念材料も多いので警戒心は常に持っていたほうが良いと思います。
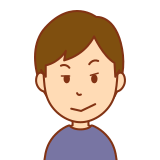
一時期よく聞いた「メタバース」の話題もそうですが、こういった記事ってプラットフォームを開発した企業の熱意を感じてしまうんですよね。今年が「ライブコマース元年に”なるかもしれない”」って書き出し自体、暗に現時点ではライブコマースは浸透しておらず、浸透するにしてもこれからだというのを自ら認めていると思います。
コロナ禍前のメルカリや楽天といった先行事例の失敗を紹介しつつ、コロナ禍を経て新たな可能性が出てきたと展開しているのがこの記事です。記事冒頭ではTikTok Shopの開始予定を伝えており、中国市場のライブコマース盛況や、日本でのユニクロの事例を取り上げて、これからライブプラットフォームは本格化するとしています。
どちらかと言うと、この記事は消費者向けでは無く、現在ECを展開している事業者向けの記事なんだと思います。
編集後記

テレビショッピング的な感じかなぁ。購入まではしないけどジャパネットとかのCMみてると欲しくなったりするからライブコマースが一般的になってよく目にするようになったら購入までいくかなぁ。



コメント