2025年のゴールデンウイーク(GW)は、4月26~27日、29日、そして5月3~6日が休みとなる「飛び石連休」になる見通しだ。平日に休暇を取ることで、最大で11連休にすることも可能だ。日頃の疲れを癒やすためには、この連休をどのように過ごすのが良いのだろうか。産業カウンセラーの渡部卓さん(68)に話を聞いた。

◇上司が休まない会社は…
「日本は真面目な人が多く、長く休むと『こんなに休んで申し訳ない』と思ってしまうのではないでしょうか」
職場のメンタルヘルスやコミュニケーションに関する講演や企業向け研修で講師を務める渡部さんは、このように語る。
かつて企業で管理職を務めていた渡部さんは、「誰かが休んで職場で困ったことが起きた経験は全くなく、管理職でそれを気にする人は今の時代ではいないと思います」と述べ、積極的に連休を取得することを勧めている。
厚生労働省のデータによると、2023年に企業が従業員1人に対して付与した年次有給休暇(日数の繰り越しを除く)は平均16.9日。そのうち実際に取得された日数は平均11.0日だった。
取得率は65.3%と、1984年以降で過去最高を記録したが、政府が2028年までに目指している70%の目標には届いていない。
また、2024年の調査では「年次有給休暇を取得する際のためらいの有無」を尋ねたところ、「あまりためらいを感じない」「全くためらいを感じない」と答えた人の割合は、合計で60.8%となった。
一方で、「ためらいを感じる」「ややためらいを感じる」と回答した人は合計で39.2%にのぼり、「感じない」とする回答よりは少数派ではあるものの、約4割の人が休暇を取ることに対して抵抗を感じていることが分かる。
では、休暇取得にためらいを感じる人と、そうでない人との違いはどこにあるのだろうか。
調査報告書では、その要因の一つとして「直属の上司が積極的に年次有給休暇を取得しているかどうか」が挙げられている。実際に、上司が休暇を積極的に取得していないと答えた層では、「ためらいを感じる」と答えた割合が29.8%と高くなっていた。
米国企業での勤務経験もある渡部さんは、「海外では休日にキャンプに行ったりカヌーをしたりして、携帯電話が通じないということも普通です。『しっかり休んだ人の方が仕事ができる』という考え方をしています」と語る。
さらに、こう提言する。
「特に管理職の人ほど率先して長く休んでほしいと考えます。上司が休んでいることが見えないと、若手社員は自分が休むことを申し訳なく思ってしまいます。連休明けのメンタル不調を予防するためにも、管理職も若手社員も休むことは大切です」
では、連休を有意義に過ごすにはどんな工夫ができるのか。
渡部さんが勧めるのが「五つのR」
- ◇Relaxation(リラクセーション)
自律神経を整え、心身のバランスを回復させる=腹式呼吸、アロマセラピーなど - ◇Rest(レスト)
体をしっかりと休めること=十分な睡眠やマッサージなど - ◇Recreation(レクリエーション)
思いきり遊び、楽しみ、笑う時間=スポーツ、キャンプ、映画鑑賞など - ◇Retreat(リトリート)
日常を離れ、静かな環境で心身を癒やす=旅行、森林浴など - ◇Resilience(レジリエンス)
ストレスに打ち勝つ力を養う=読書やセミナーで心理学やストレス対処法を学ぶこと



日本人にとって馴染み深いのは「レクリエーション」。休日にレジャーや遊びに出かけるという考えは広く浸透している。
ただし、渡部さんは「リラクセーション」「レスト」「リトリート」も「実現できるチャンス」と捉え、連休中にこれらを意識的に取り入れることを勧めている。「バランスよくやってみてはいかがでしょうか」と提案する。
最後に紹介されている「レジリエンス」は、「バネのような弾力性」「ゴムのような粘り強さ」といった回復力を高めることを意味し、ストレスや悩みを別の角度から見つめ直すきっかけにもなる。
「本で学んだり、セミナーに参加して語り合ったり、休み中だけでも日記を書いたりすると、自分を見つめ直すことができます。連休の過ごし方にレジリエンスを組み合わせてみてください」と話している。
日本人にとって馴染み深いのは「レクリエーション」。休日にレジャーや遊びに出かけるという考えは広く浸透している。
ただし、渡部さんは「リラクセーション」「レスト」「リトリート」も「実現できるチャンス」と捉え、連休中にこれらを意識的に取り入れることを勧めている。「バランスよくやってみてはいかがでしょうか」と提案する。
最後に紹介されている「レジリエンス」は、「バネのような弾力性」「ゴムのような粘り強さ」といった回復力を高めることを意味し、ストレスや悩みを別の角度から見つめ直すきっかけにもなる。
「本で学んだり、セミナーに参加して語り合ったり、休み中だけでも日記を書いたりすると、自分を見つめ直すことができます。連休の過ごし方にレジリエンスを組み合わせてみてください」と話している。
専門家の反応は?
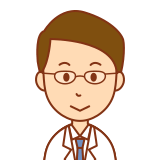
GWの過ごし方が話題になる時期ですね。ぜひ、普段に生活で消耗してしまったエネルギーの補充を最優先にして下さい。
張り切って予定を詰め込み過ぎず、「寝正月」ならぬ「寝GW」でもまったく構いません。そのうえで、心身ともに余裕があれば非日常的な体験でワクワクする時間もある休みにして欲しいですね。
ただ、『GW?そんなの関係ないよ…』という人もいます。たとえば、入院患者さんを扱う医療スタッフ、交通を支える駅員さん、飲食店やスーパーの店員さんなど、言い出したらキリがありません。
休みたいのに休めない人もいることも忘れたくないですね。たしかに、普段から言い慣れてないと、感謝を伝えるのは照れくさいかもしれません。
ただ、連休中こそ対応してくれたスタッフに向けて、『ありがとうございます』と口にするいい機会でもあります。その一言があるだけで、お互いにとって、より心地よい時間や空間になるはずです。
ネットの反応は?
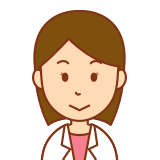
私は精神科で勤務する医療従事者です。休む、働くということに関して日本人は欧米と比べると区別をきっちりとしたがる国民性があると思います。穢と晴れですよね。そういうことで悩みを持っている患者さんが多い。明日1日働いたら休みだ。ああ、明日から仕事だ辛い。という風に区別をハッキリしたがる。なので遊ぶように仕事をし、働くように一所懸命に遊ぶ、という意識を持ってみる。認識を変えてみる。そういうことで楽になることってあるのではないかと思います。物理的なことを変えるのは大変ですが、自分の認識を変えるのは比較的簡単なことですから。
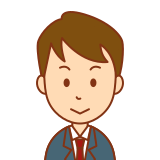
メンタル不調の予防ということであれば、GW後の祝日が無い期間に、複数の有給休暇を取りやすくしておく事が、職場として大事ではないでしょうか。 むしろ上司が積極的に前もって5月下旬ぐらいに長期休暇を予定していると公言しておけば、周囲は「そういう取り方をしても良いんだ」という安心感になると思います。
編集後記

記事内にある「誰かが休んで職場で困ったことが起きた経験は全くなく」って本当にそうで、2.3日連絡が取れないくらいでは本人が気にするほど何か職場の人に迷惑をかけてしまうって事はそうそうないんですよね。



コメント